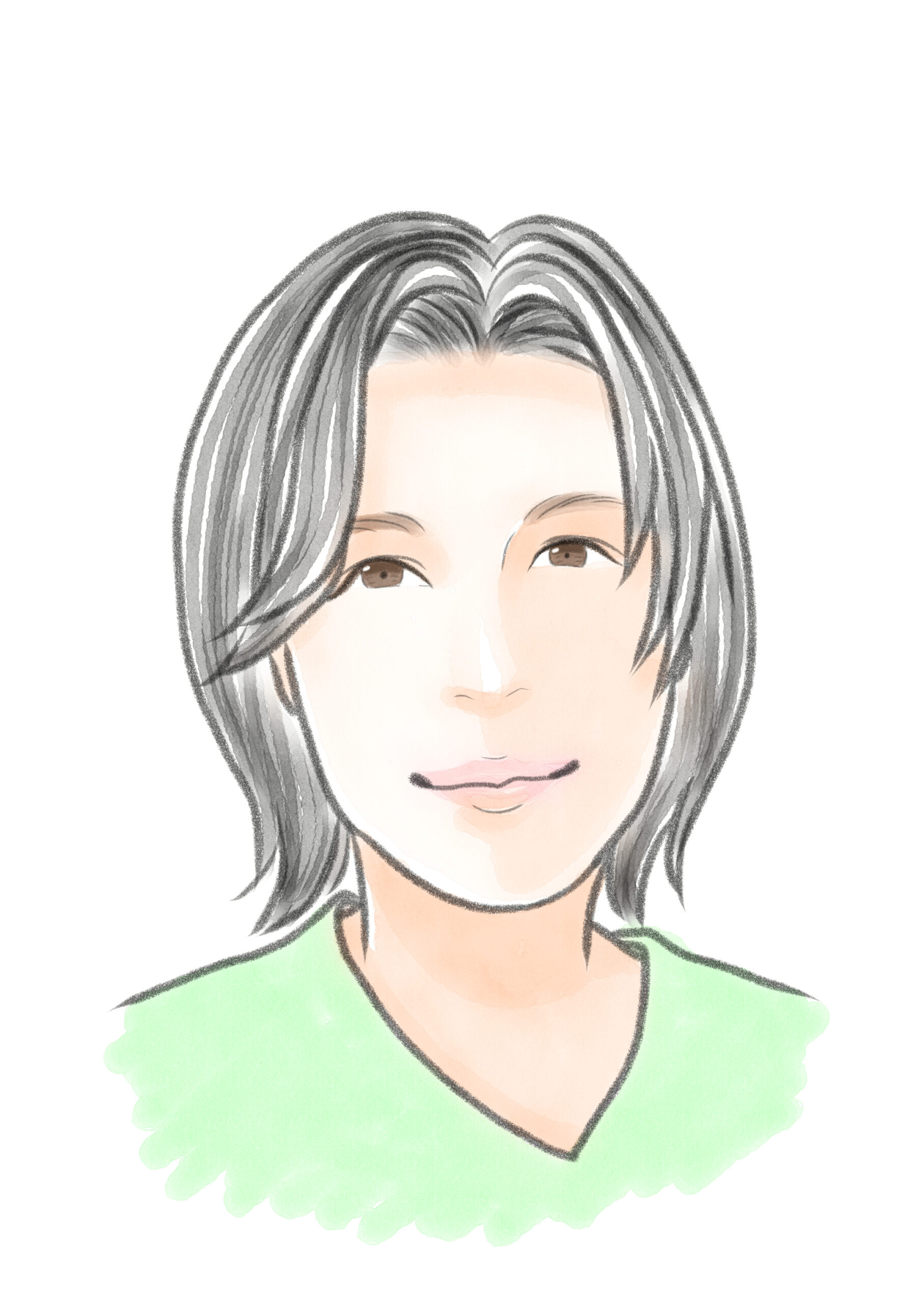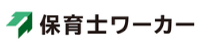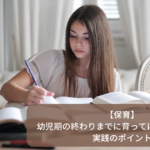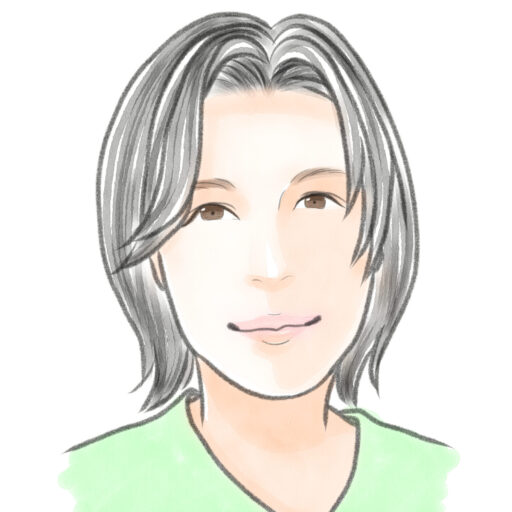書く:
この記事で解決できるお悩み
・週案を書く時のポイントが知りたい
・週案の具体的な書き方
・年齢別の週案の書き方のコツ
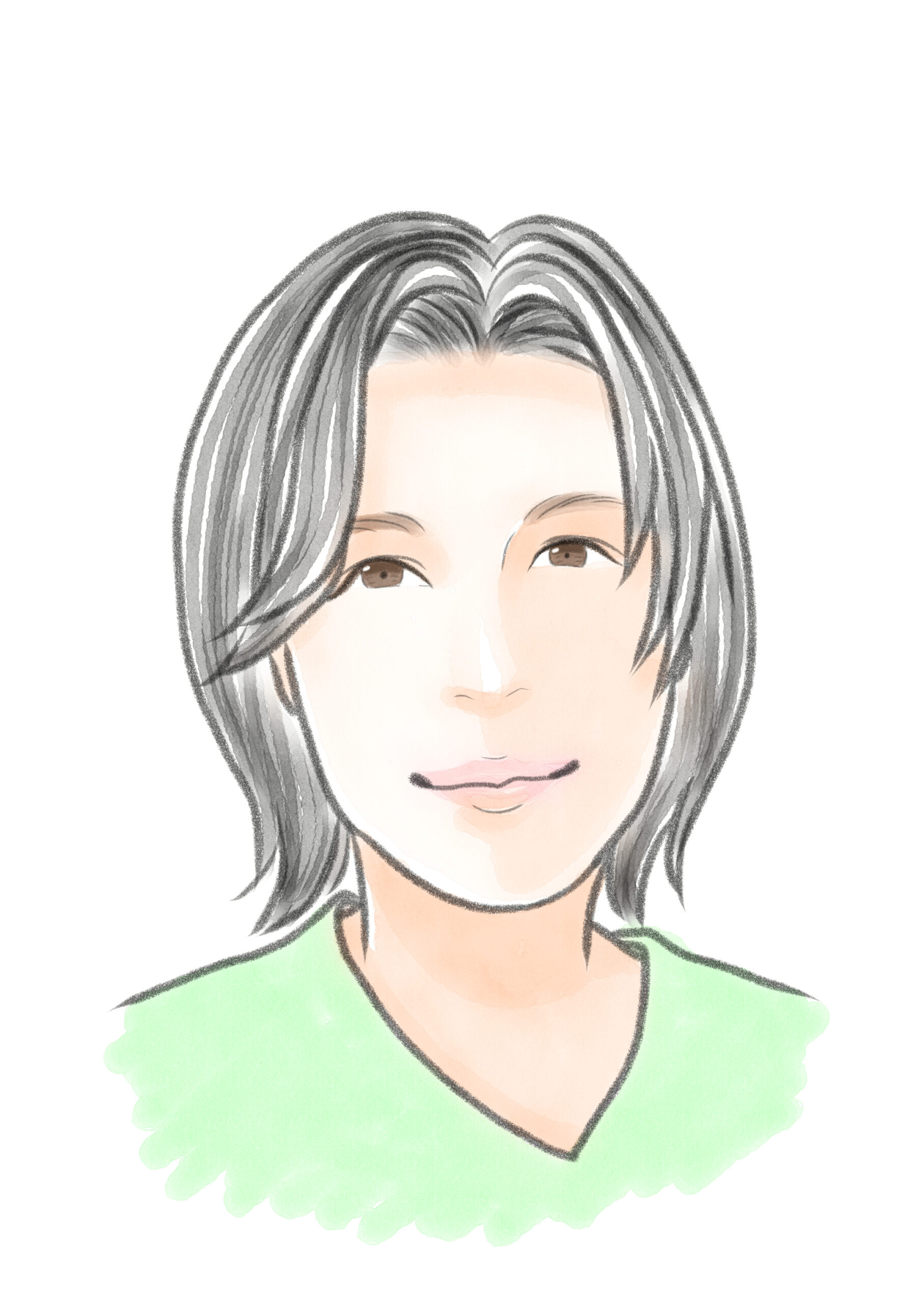
保育雑誌やネット検索での週案を丸写しするという方も少なくありません。
しかし、雑誌やネットにある週案の事例は、どうしても目の前の子どもの姿とズレがあったり、行事や園での保育と週案例が合わなかったりすることもありますよね。
ここで、朗報です。
実は、週案を書く時には、抑えるべきポイントがあります。
つまり、そのポイントが分かっていれば、週案も書きやすくなりますね。
ちなみにこの記事の信憑性として、私は、クラス担任を持っていた時には、週に1回ペースで立案していましたので、週案は600回以上書きましたし、主任、園長になってからは、1,500枚近くの週案を見てきました。
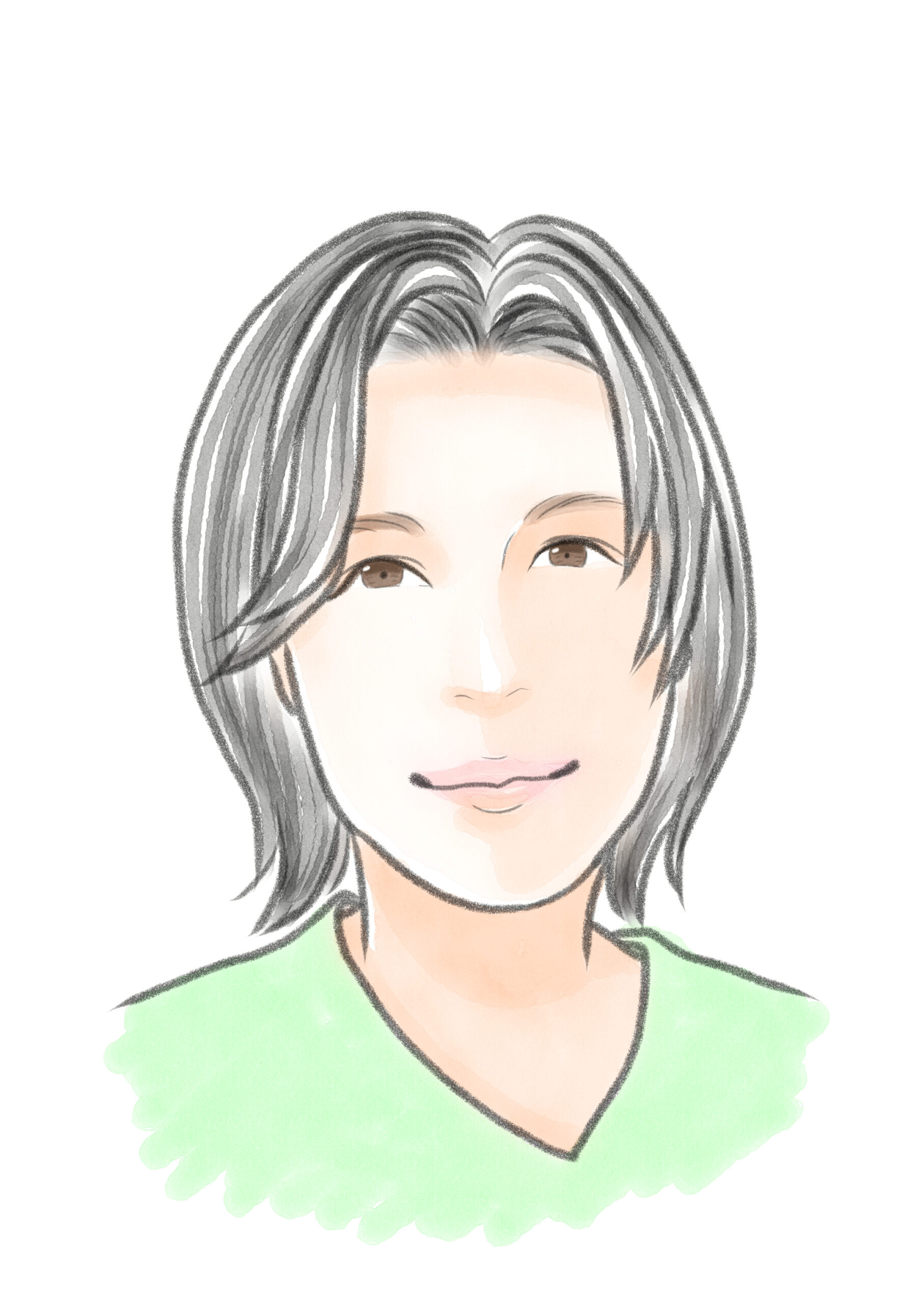

|
第1位:保育士ワーカー
|
総合評価//保育士ワーカー口コミ |
| 非公開求人の閲覧可能 入社後のフォロー体制◎ |
|
| 求人数:約20,000件 | |
| 第2位:保育のお仕事
|
総合評価/ |
| 企業法人内の内部事情に精通 幼稚園教諭求人にも強い |
|
| 求人数:約19,000件 | |
| 第3位:保育求人ラボ
|
総合評価/ |
| 様々な雇用形態に対応可 担当アドバイザーの対応◎ |
|
| 求人数:約24600件(2023年9月現在) |
こちらもCHECK
-

-
【現役園長が教える保育のおすすめの本決定版】目的別に厳選紹介!
続きを見る
こちらもCHECK
-

-
【保育】10の姿とは?幼児期に育ってほしいポイントや実践を解説
続きを見る
週案とは?
そもそも週案とは、週単位の保育の指導案(保育計画)であり、その週案の中で、ねらいや内容、保育士の環境設定や配慮についてまとめたものとなります。
保育の中には、他にも年案、月案、日案というものもあります。
年案では1年の目標や計画あり、それらを達成するために、月単位の月案を立案し、月単位のねらいを達成するために週単位の週案を立案するという風に、1年間を細かく分けて作成しています。
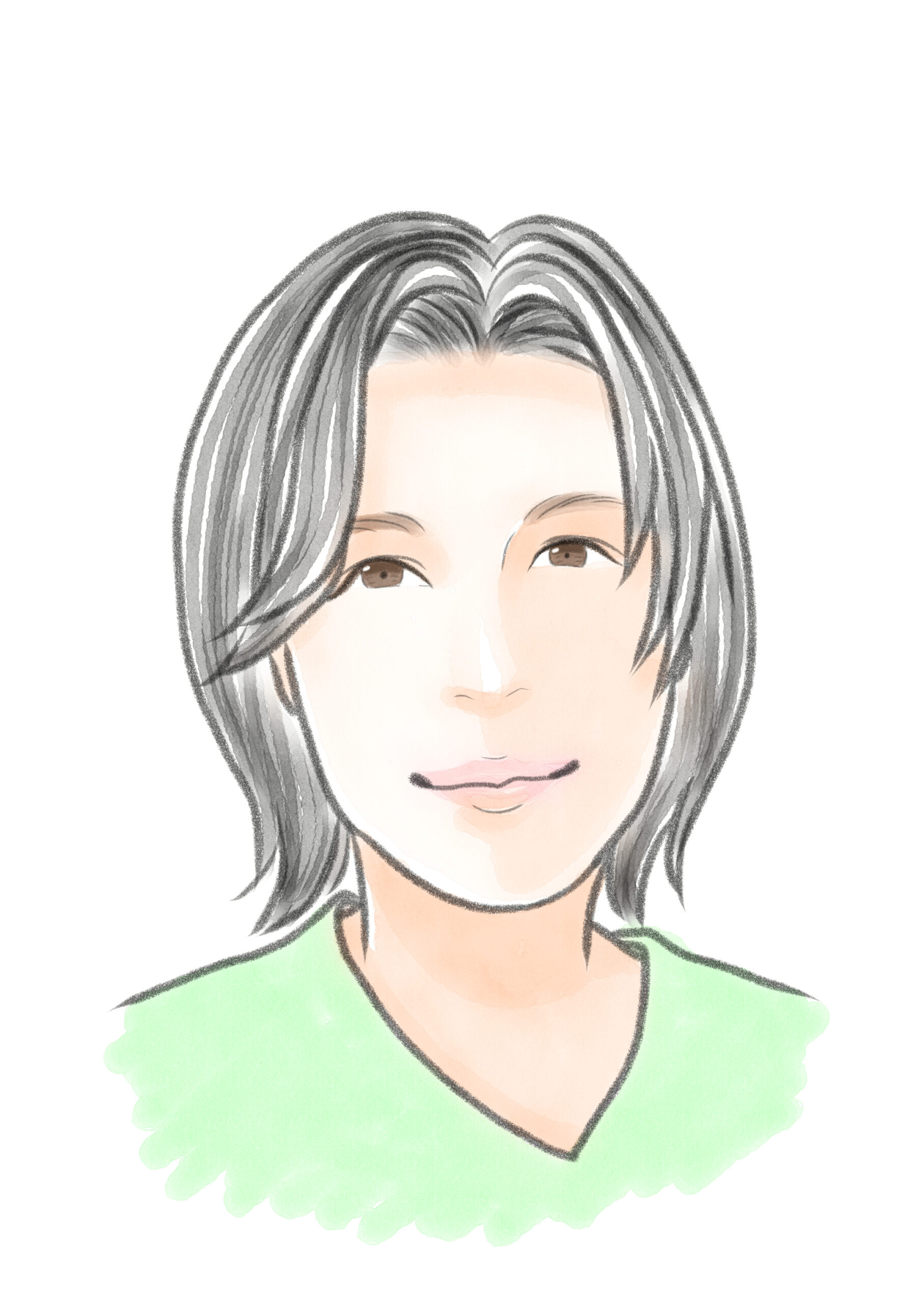
週案の内容項目について
次に、週案の内容について触れていきます。統一の書式があるわけではないので、県や市、法人などによって様々な書式がありますが、共通している項目について解説していきますね。
子どもの姿
子どもの姿は週案の基礎となる部分であり、重要になってきます。
先週からの引き続きで、子ども達の姿を予測して書いていきましょう。
具体的に、どんな遊びをどのように楽しんでいたのか、遊び以外では、友達関係の変化や生活習慣の自立面での変化などありますね。
注意点としては、1人の子の予測する姿だけに偏らない事です、
当然のことながら、一人一人発達段階は異なり、同じ活動や遊びであっても反応や興味関心の示し方は異なるからです。
個々の姿だけでなく、小集団(友達)やクラスとしての集団という視点で考えてみましょう。
ポイントとしては、週案を立案する時に姿を思い出し書いていくのではなく、普段から上記の視点で子どもを観察していくことです。
子どもの姿の具体的な書き方
この子どもの姿は大切です。
では、子どもの姿をどのようにとらえるのかを考えていきましょう。
子どもの姿は、5W1Hで書く
まずは、結論です。
有名な5W1H、これを使って子どもの姿を見ていきます。
ポイント
「When→いつ(時間)」
「Where→どこで(場所や空間)」
「Who→誰がor誰と」
「Why→なぜ(心情、行動)」
「How→どのように」
要するに、この5つの視点から見ていくということです。
このように、5つの視点から子どもをとらえることで、細やかな子どもの捉えに繋がるからです。
今日(今週)、なにしてたかな?という捉え方では、〇〇くんが、〇〇をする姿が見られた。という感じになりますね。
子どもの姿「When→いつ(時間)」
さぁ、では、この「When→いつ(時間)」は何を見るのでしょう?
これは、そのまま時間です。
とは言え、1日の中で、何時から何時まで遊んでいたというような細かい時間ではありませんよ。
クラス全体で、その子どもの姿は、1日、1週間の中で、どの程度あったのか?ということです。
極端な話、その姿が1日のほんの数分の姿しかないのに、来週のクラスの週のねらいはそこから考えようとはならないですよね。
ワンポイント
個人、小集団、中集団、クラス全体と分けてみると良いですね。
「Where→どこで(場所や空間)」
次に、場所ですね。
単純にどこでということもありますが、年齢が上がるにつれ、遊びの場所や空間を自分たちで考えていく、作り出していくという姿も当てはまると思います。
子どもの姿で、どこで遊んでいたのかは、文章に入れるこては少ないと思いますが、子どもの姿を捉える上では、重要な要素になりますね。
「Who→誰がor誰と」
次に誰が?もしくは、誰と?です。
これは、人とのかかわりの部分ですね。
年齢が小さいですと、一人遊びから始まりますので、誰がということは、自分、または、保育者になると思います。
少しずつ、人とのかかわりが広がってくると、「誰と」が友達や小集団と変わっていきますね。
ポイント
友達とのかかわりに変化が出始めた時に、特に注意して観察してみましょう。
「Why→なぜ(心情、行動)」
どんなことをしていたのか、遊んでいたのかではなく、なぜ?そのような姿が見られるのか観察してみましょう。
そのなぜ?の部分が変化していくことは、何かの力が育まれているという事です。
また、行動面だけでなく、心情、意欲の部分の変化も見ていきましょう。
ポイント
姿の変化が、初めは見ていた姿から、近くに寄ってくる、自分でやってみるという姿には、心情や意欲がどのように変わっていったのか書いてみると子どもの姿が具体的になりますね。
「How→どのように」
どのようには、表面的な〇〇をして遊んでいたではなく、具体的に何をどのように遊んでいたのか観察してみましょう。
例えば、「積み木遊びを楽しんでいた」では、積み木遊びをしていたことは分かりますが、どのように楽しんでいたのかが分かりません。
積木は、積むことも、同じ形のものを集めることや、崩すこと、大型積木で見立てて遊ぶことなどあります。
例えば、年齢が小さく、色の積み木で、同じ色を集めているのであれば、視覚認知が育まれているのでしょうし、同じという概念、色の概念も形成されていくでしょう。
このように、どのように、何を楽しむということを細かく観察することは、子どもの姿や成長の捉えていくことにもつながっていきます。
ねらい
週案のねらいは、子どもの姿から、その週で目指していく子どもの姿の変化や成長、興味関心の深まりなどの視点から書いてみましょう。
ポイント
保育所保育指針に、保育のねらいを5つに分類したものが記載されていますので、参考にしてみると良いですね。
保育所保育指針は、文字ばかりで読み進めていくことが大変と思う方は、保育所保育指針の内容をイラスト付きで解説している本がおすすめです。
内容
内容とは、その週のねらいを達成、近づけていくためには、どの様な経験や活動が必要なのかを具体的に書いていきます。
ねらい同様に子どもの姿や発達から経験が可能な活動にしていきましょう。また、クラス活動だけでなく、自由遊びの中での友達とのかかわりから芽生えることも重要ですので、年利や時期、姿に合わせ遊び、生活、クラス活動を充実させた内容にしていきましょう、
ねらいと内容を整理する
ここも、迷ったり、分からなかったりと悩む人が多いと思います。
ただ、整理することで、週案が書きやすくなりますよ。
ねらい
- 子どものどんなところを育てていきたいのか
- 子ども達がどんな風に育ってほしいのか
ですから、この週のねらいで、
ボタンをとめる、ロッカーのマークを覚えるのように感じのねらいだと子どもに何かをさせるということになり、子どもにあったねらいに適しているとは言えませんね。
子どもに達が、遊びや生活の中で、繰り返し行う中で、態度として、最終的にボタンをとめる、マークを覚えるという姿に繋がっていくということです。
これは、身の回りのことを自分でやってみようとする気持ちが育ち、実際にやってみようとする気持ちが芽生え、自分でどのように行うのか習得していくということですね。
ここが、混ざってしまうことが多いですね。
では、内容とは?
内容
- ねらいを達成するために必要な経験
このように、シンプルに考えてみましょう。
このように整理できると、「〇〇遊び」は、内容ではなく、遊びや活動の部分に書くことが分かってきますね。
保育者の援助
ここには、その週の保育をする上で、配慮すべきことや子どもへの関わり、援助の仕方を具体的に記入していきます。
身体面での援助だけでなく、情緒面の援助も大切ですので、整理すると良いですね。
また、子どもの姿、活動から予想される子ども同士のトラブルも予測し、状況に応じた援助を考えておくと更に良いですね。
日々の記録・評価反省
週案には、日々の記録や一週間の振り返りを各項目があります。
この記録や評価反省は、次週の週案に繋がっていくので、書く視点を覚えておきましょう。
日々の記録と週の振り返りは日記にしない
新しい週案を作る時に、前の週の記録、反省が、しっかりと書けていると週案の作成が早くなりますね。
では、どの様に日々の記録を書くと良いのでしょうか。
「今日は、〇〇遊びをして、子どもたちも楽しそうに遊んでいた」
これに似たような文章になることはありますか?
これがいわゆる日記です。
ここまで、極端でないにしろ、〇〇をしました、次は、〇〇したいという感じですね。
ずばり、ここを改善しましょう。
どう書くと良いのかよりも、何を書けばいいのかを考えてみましょう。
ポイント
・日々の記録や週の反省では、ねらいに対して、子どもの姿の変化はどうだったか?
・保育士のどんなかかわりで、どの様な姿になったのか?
・立案したねらいは、子どもの姿に合っていたのか?
という視点を持つと書きやすくなると思います。
先程の〇〇遊びをしました。
という書き方ではなく、このように書いてみてはいかがでしょうか。
具体例
◆◆というねらいに対して、〇〇遊びをしました。その中で□□のかかわりをすると、子どもの姿が▲▲から●●に変わっていった。
◆〇▲●の部分を変えてみるといいですね。
これで、1週間の反省でも、子ども達の変化が成長の部分や新しい力の芽生えなのかが分かります。
自分のかかわり方もどうだったか振り返りやしやすいですね。
週案の書き方5つのポイント
それでは、もう迷わない!週案の書き方5つのポイントをお伝えします。
5つのポイント
- 先週の子どもの姿が大事
- 年案と月案に統一性、整合性を持たせる
- 園の保育理念や保育方針に沿う
- 言葉の意味を理解する
- 言葉の言い回しは、本を参考にする
ポイント①:先週の子どもの姿が大事
週案は、月案を1週間に落とし込んで立案し保育していくことは先ほど触れましたね。
ですから、前の週の子どもの姿を踏まえて週案を立案することが大事になってきます。
前の週で、子ども達は遊びを楽しんでいただろうか、友達とのかかわりでトラブルが起きやすかった場面は?など細かい姿を把握して週案を作ることが大事です。
その他にも、季節の移り変わりでは、気温の変化によって保育内容も変わりますので、季節や天候にも情報の視野を広げておくことも大切になってきます。
保育者主体で、保育者が決めた活動ばかりする保育にならないようにしたいものですね。
子ども主体の保育になるように、週案も立案した時の計画にこだわりすぎずに臨機応変に保育していけると、保育がもっと楽しくなりますね。
ポイント②:年案・月案と統一性を持たせる整合性を持たせる
先ほども触れましたが、年案があり、12か月に細分化した、さらに1週間に落とし込んだものが週案です。
ですから、週案、月案、年案の関連性が全くないとなると、行き当たりばったりの保育という事になります。
ですから、週案は、月案や年案との関連性を意識して週案を立案し、整合性を持たせていきましょう。
年案は、年間の終わるの目標を達成していくための計画であり、行事も含まれ長期的な見通しの計画になります。
一方で、実際の保育では、年案での見通しと異なることも出てきますので、その様な視点を年案の評価反省や記入し、可能な範囲で計画を修正していくことも大事ですね。
ポイント③:園の保育理念、保育方針に沿う
理念とは簡単に言うと、その保育園の目指す保育、大事にしている部分を表しています。
その核となる保育理念に向かい、保育の方針を定めていきます。
保育方針は、保育園ごとに違います。
しかし、保育方針とは、どのような保育をしていくのかを表す、いわゆる道しるべなのです。
ですから、理念や方針に沿って立案していくことで、次の年齢への繋がりもでき、子どもの育ちに沿ったものになるでしょう。
ポイント④:言葉の意味を理解する
立案する際に、言葉の意味を理解し子どもの姿に合った言葉を選んで書きましょう。
例えば、週案でよく見かける「〇〇を楽しむ」、「〇〇を味わう」これらの言葉。
楽しむという言葉は、子どもの感覚的な部分、興味関心を持って取り組んでいる様子という意味合いです。
一方、味わうとは、楽しさや嬉しさなど繰り返し経験したうえで感じることですので、楽しむよりも深い様子の意味合いです。
他に、年齢の発達に合った言葉も選びましょう。
例えば、「友達との関わりを楽しむ」という姿。
0歳、2歳の低年齢でも一緒に遊んでいるように、関わってるようにする姿があります。
とは言え、実際に友達との関係を築き深めていく時期は少し後になっていきます。
この様な視点で立案していくと目の前の子どもの姿に合った週案になると思います。
ポイント⑤:言葉の言い回しは、本を参考にする
本に書いてあるねらいは、目の前の子どもたちのねらいに一致するとは限らないというお話をしました。
ですから、姿やねらいは参考程度にと思います。
しかし、言い回しや言葉の選び方は、真似できるところがたくさんあると思いますので、週案を書くのに慣れるまでは、何冊か持っていると便利だと思います。
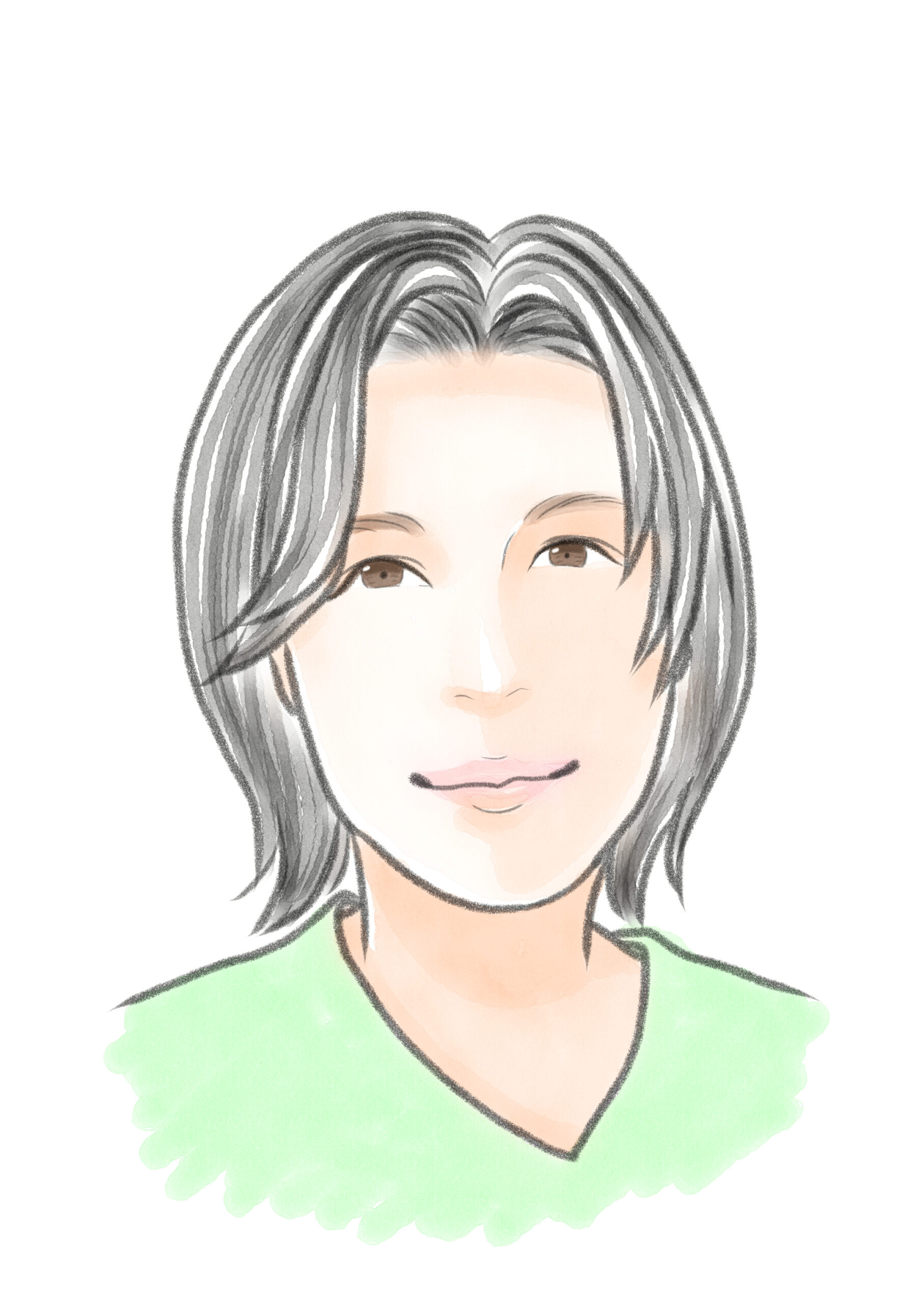
週案を書く時におすすめの本
おすすめ①:子どもの姿ベースの新しい指導計画の考え方 新要領・指針対応
ポイント
- 「子どもの姿」をベースに指導計画を考えていくという、子ども主体の指導案作成に参考になります。
- 育みたい資質や10の姿を漫画やイラストで分かりやすく解説されていますので、保育所保育指針の理解も深まります。
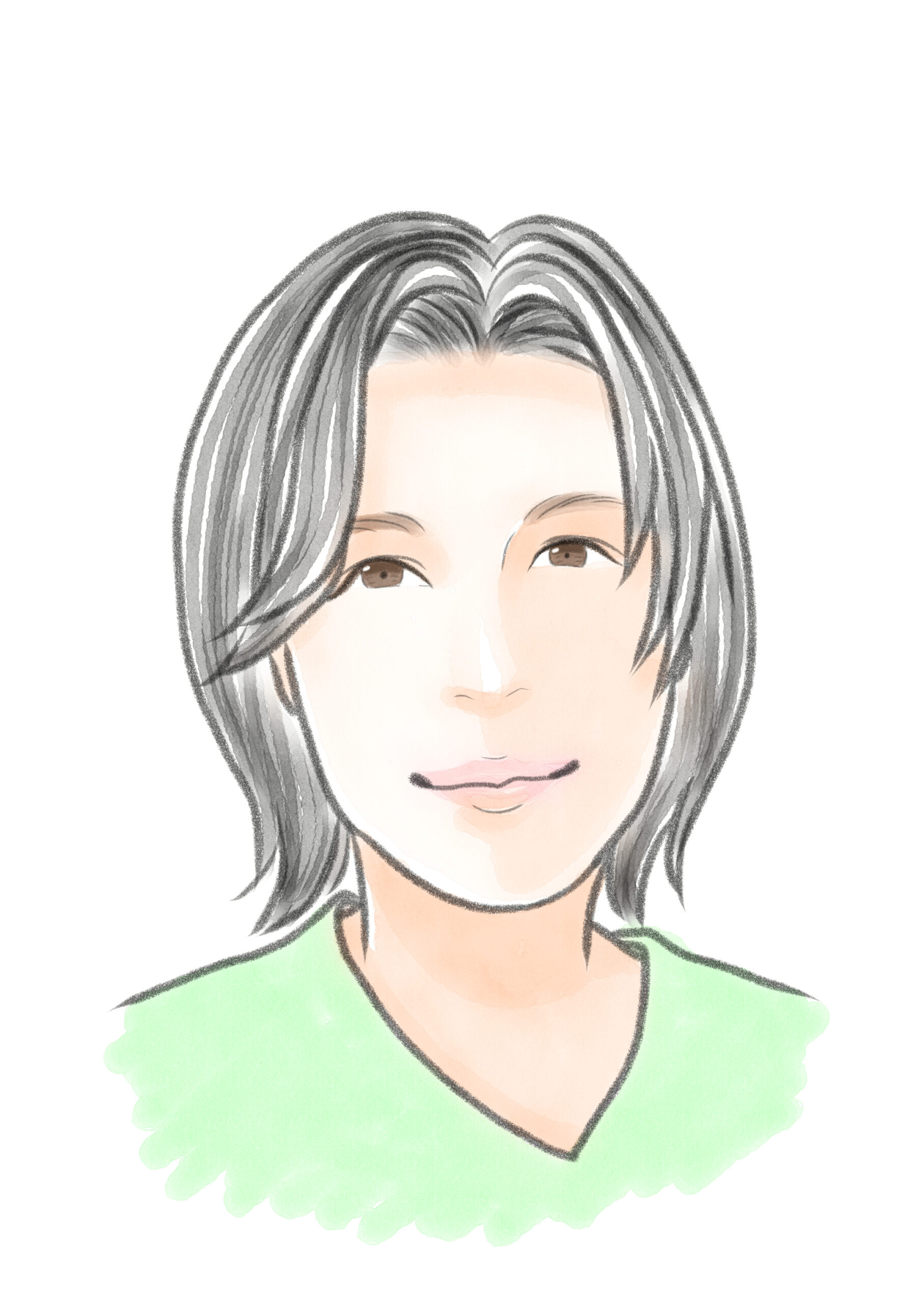
おすすめ②:0~5歳児指導計画の書き方がよくわかる本
ポイント
指導計画を書く上で教科書の様に分かりやすい内容となっています。各年齢(0歳児、1歳児、2歳児、3歳児、4歳児、5歳児)のねらい・内容が解説されています。また、例文や書き方の理由も丁寧に解説されていますので、指導配慮、環境構成など、保育理解を深めたい人に特におすすめです。
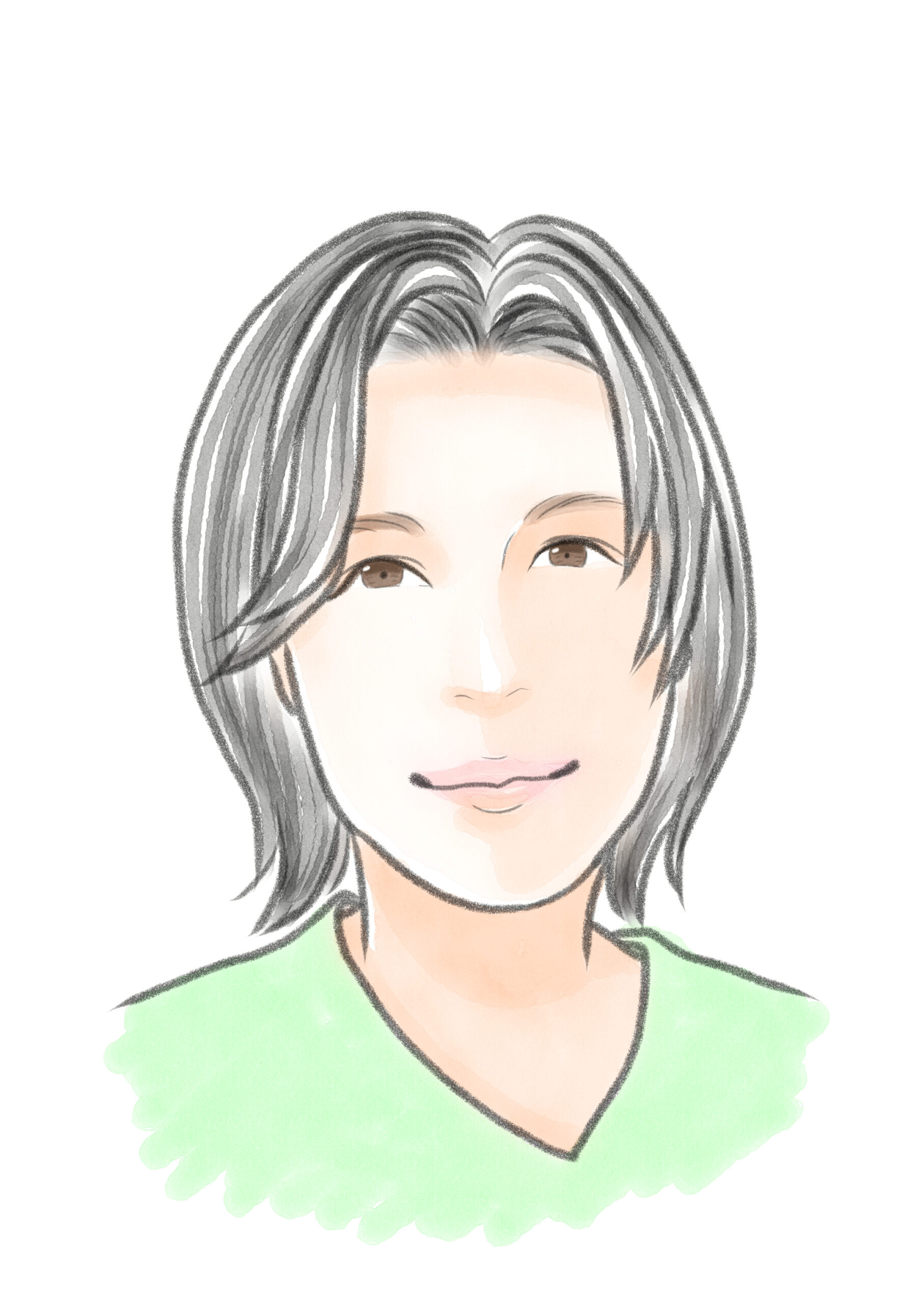
おすすめ③:カンファレンスで深まる・作れる 配慮を要する子どものための個別の保育・指導計画
ポイント
特別に配慮を必要とする子ども理解を深めていくポイントが解説されています。子どもを理解する上でのポイントは、全子ども共通ですので、子どもの姿を捉える力を高めていきたい方には特におすすめです。
指導計画の本を選ぶポイント
本を選んでいくときには、自分が、何を目的としているのかを明確にしましょう。
言い回しや文章表現であれば、年間の指導計画が記載されているものがおすすめです。
指導計画の根本や意味合いや子ども理解を目的とるのであれば、上記の3冊の本はおすすめです。
子どもの発達を幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿から捉えていきたい方は、こちらの記事がおすすめです。
こちらもCHECK
-

-
【保育】10の姿とは?幼児期に育ってほしいポイントや実践を解説
続きを見る
おすすめ④:0歳児指導計画の作成におすすめの本
こちらの本は、CD-ROMが付き、例文も多く載っていますので、書き方の参考にもなります。
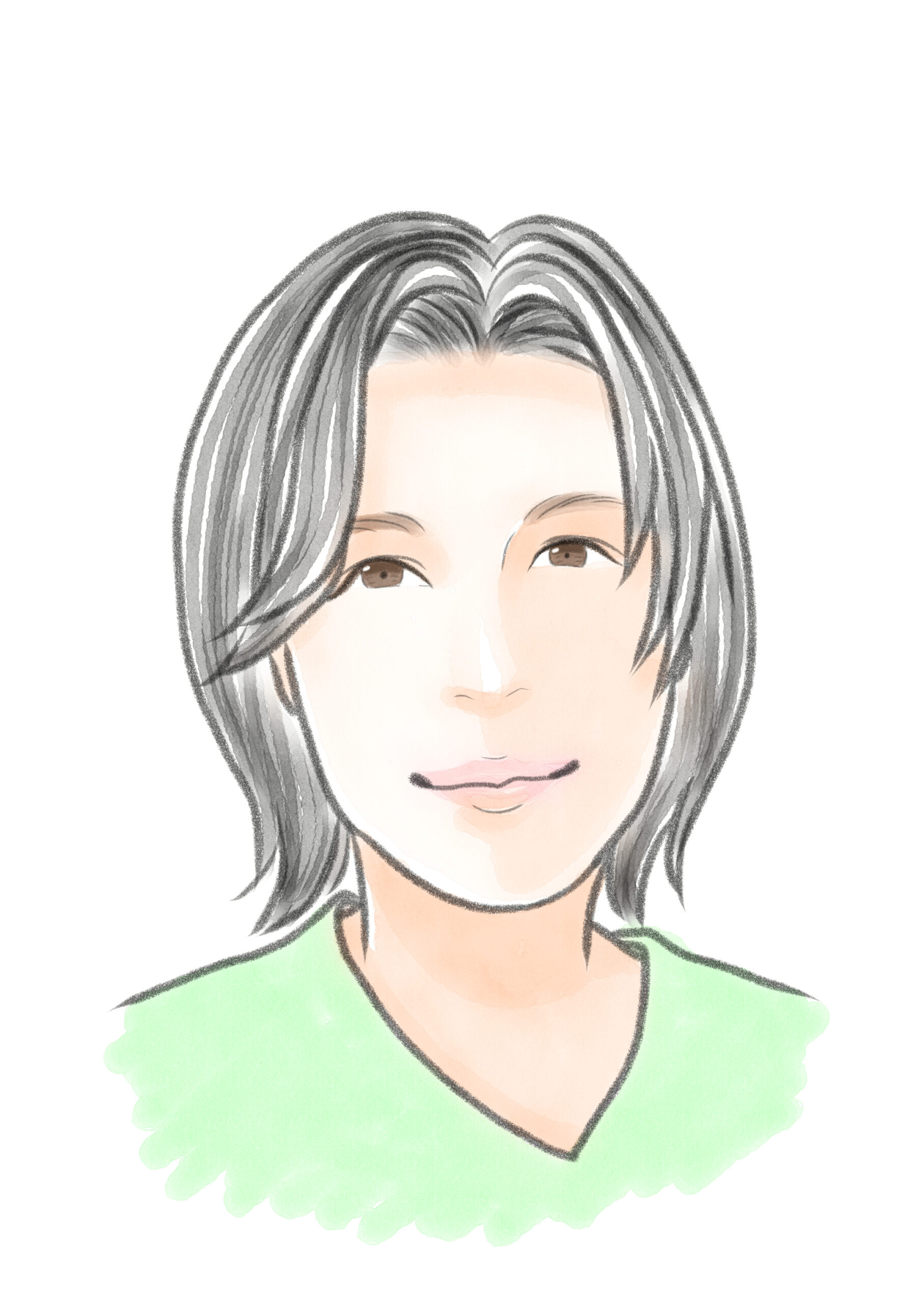
おすすめ⑤:1歳児指導計画の作成におすすめの本
こちらの本は、CD-ROM付、例文付きですので、初めて1歳児担任を持つ保育士にも安心の本です。
さらに、遊びや環境構成など 保育のポイントも丁寧に解説されていますので、保育の中で感じる疑問や問題も解決できる本となっていますよ。
おすすめ⑥:2歳児指導計画の作成におすすめの本
こちらの本は、CD-ROM付、例文付きですので、指導計画作成が苦手な人でも安心できる本となっています。
2歳児になると、自己主張も強くなってきます。自我の芽生えから、自己の確立へと移行していく段階ですので、指導計画も個々の姿に合ったものが必要になってきます。
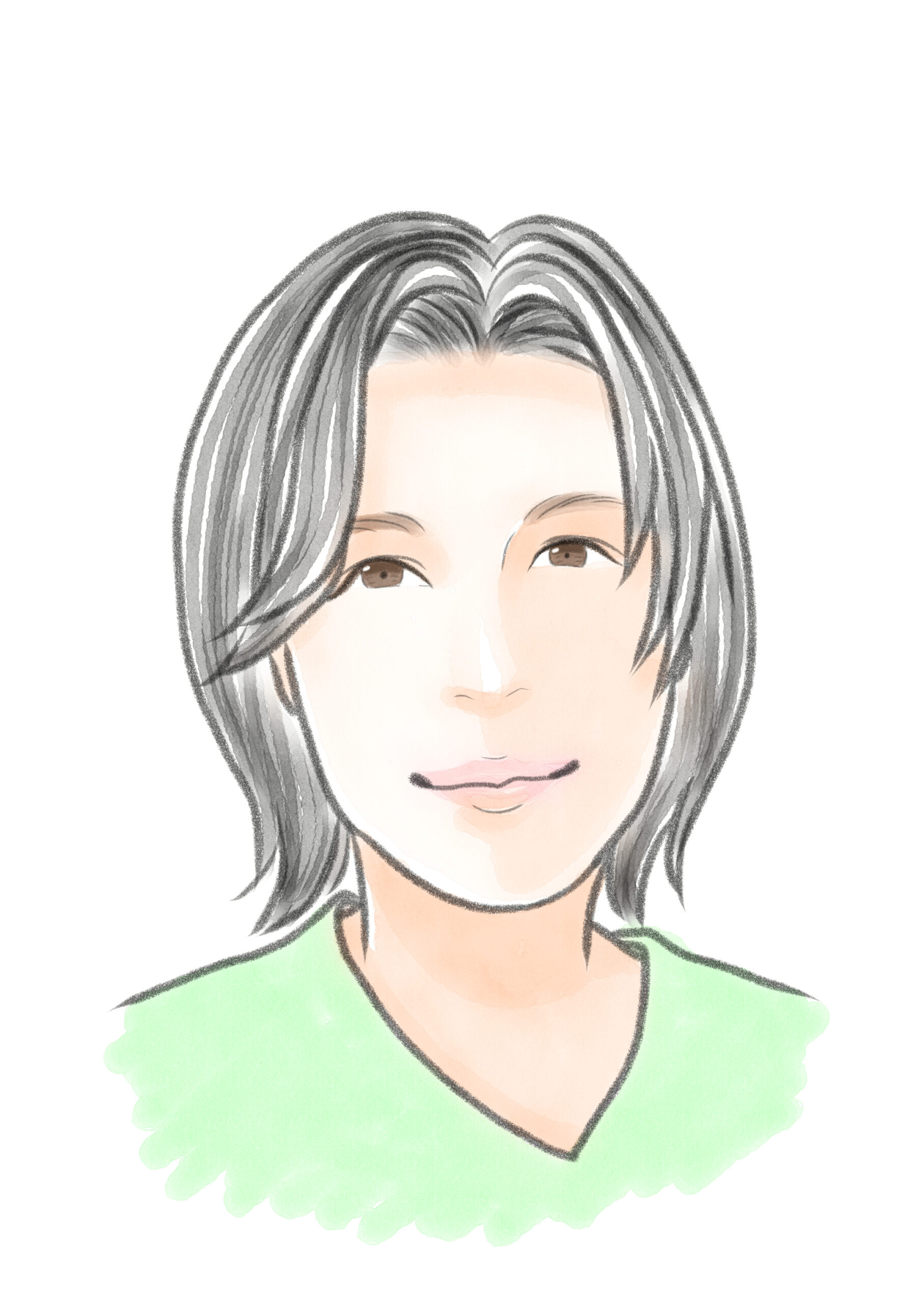
週案の書き方まとめ
それでは、おさらいしましょう。
5つのポイント
- 先週の子どもの姿が大事
- 年案と月案に統一性、整合性を持たせる
- 園の保育理念や保育方針に沿う
- 言葉の意味を理解する
- 言葉の言い回しは、本を参考にする
この5つのポイントを押さえる。
特に大事な子どもの姿の捉え方は、
「When→いつ(時間)」
「Where→どこで(場所や空間)」
「Who→誰がor誰と」
「Why→なぜ(心情、行動)」
「How→どのように」
の5W1H視点で見る。
初めのうちは、時間もかかるかもしれませんが、このポイントを押さえて慣れてくると、週案作成の時間も大幅に短縮できると思います。
週案や保育の本で参考になるものありますか?質問を受けることがありますので、指導計画作成の時のおすすめの本が知りたい方はこちらの記事を参考にしてくださいね。
その他に、保育関係のおすすめの本が知りたい方は、【保育のおすすめな本】目的別に厳選3冊を紹介を参考にしてくださいね。
こちらもCHECK
-

-
【現役園長が教える保育のおすすめの本決定版】目的別に厳選紹介!
続きを見る